弘 文 |
|||||||
弘 文
ねこ: としちん: としちん: |
弘文(大友)即位
『書紀』によると、天智は正妃・倭姫王との間には子供がなく、蘇我倉山田麻呂の娘・遠智娘(おちのいらつめ)との間に大田皇女と鸕野皇女、姪娘(めいのいらつめ)との間に阿陪皇女(のちの元明天皇)があったという。遠智娘は建(たける)皇子という男の子も産んだが、言葉が不自由だった。
天智の後継者となる大友皇子は、伊賀采女宅子娘(いがのうねめやかこのいらつめ)という地方豪族の娘が産んだ子であったとされている。
『書紀』には大友が即位したという記録はなく、壬申の乱が叔父・甥の間の皇位決定戦だったかのようになっている。
これは、勝利した大海人を「天皇を殺した叛逆者」にしないための配慮であろう。
しかし明治政府は、江戸時代に徳川光圀が著した『大日本史』に「大友は天皇だった」とあるのを正式に認め、弘文天皇という諡号を贈った。それに伴い、教科書からは壬申の乱の記事が削除されたらしい。
戦後、教科書に壬申の乱の記事が復活すると、今度は大友が即位していたかどうかが再びウヤムヤになっている。歴史とは何なのかということを改めて考えさせられる問題ではある。
| 671年 天智の子・大友皇子が太政大臣、蘇我赤兄臣が左大臣、中臣金連が右大臣になり、東宮太皇弟が詔して冠位・法度のことを施行した。 百済の鎮将劉仁願が、李守真らを遣わし、上表文をたてまつった。(『書紀』) |
東宮太皇弟とは大海人のことだが、大海人は吉野にいたはずなので、古注にある「大友皇子が宣命した」という方が正解だろう。「宣命」とは天皇の勅書という意味なので、大友はこのとき即位したとする説もある。
いずれにせよ、671年に近江朝の新体制がスタートしたことは間違いない。
その年の11月、唐の郭務悰ら二千人が再び来日した。
彼らは天智の死に哀悼の意を表し、天武元年5月に帰国したとあるが、『書紀』のストーリーでは天智は671年12月に「病死」だから、11月に来日しているのは天智の葬儀のためではありえないし、見舞いだったとしても二千人は多すぎる。
彼らは、やはり今回も大海人のクーデターに加勢するための軍隊であった。
もちろん唐の正規軍ではなく、郭務悰の蓄えた私兵である。
朝廷側も、いよいよ決戦のときが来たとして、『書紀』にはこの直後、大友が手に香炉をとり、蘇我赤兄らと6人で「天皇の詔を承る」誓いの場面がある。
12月、天智の病死を伝える記事があるが、670年に行方不明になった天智の死がこのとき公表されたとするならば、大友が正式に即位式を挙行したのは明けて672年、壬申の乱の年だったと思われる。
天武が即位したのは天武2年(673年)の2月となっている。
普通は即位した年が元年のはずだから、その前年を元年としている理由は、第一に、弘文朝を抹消するためである。672年は、本当は弘文元年だったのだ。
第二に、郭務悰らが帰国したのを「天武元年5月」とし、彼らが天智の葬儀のためにだけやって来て、壬申の乱には介入していないかのように見せかけるため。この「天武元年」は、文字通り天武が即位した年(673年)という意味で使われているのだ。
郭務悰の率いる唐人の軍のみならず、新羅軍もまた壬申の乱に介入し、筑紫太宰府や吉備地方を押さえ込み、吉野軍の勝利と天武の即位を見届けてから帰国したというのが真相である。
高市皇子
吉野軍が勝利した最大の要因は、外国勢の後押しがあったこと以上に、高市皇子が近江朝を裏切り、大海人軍の総大将となったことである。
『書紀』に次のようなエピソードがある。(なお、これは天武条にある記述なので、文中の「天皇」とは、まだ即位する前の大海人のこと。)
| 天皇は高市皇子に、「近江の朝廷には左右の大臣や知略にすぐれた群臣がいて、共に謀ることができるが、自分には事を謀る人物がいない。ただ、年若い子供があるだけである。どうしたらよいだろう」と言われた。 皇子は腕まくりをして剣を握って、「近江に群臣あろうとも、どうしてわが天皇の霊威に逆らうことができようか。天皇はひとりでいらっしゃっても、私高市が神々の霊に頼り、勅命を受けて諸将を率いて戦えば、敵は防ぐことができぬでしょう」といわれた。天皇はこれをほめ手を取り背を撫でて、「しっかりやれ、油断するなよ」といわれた。乗馬を賜わって、軍事をすべて託された。 |
大海人の長男は草壁、次男は大津、そして高市は三男とされているが、天武が「(自分には)年若い子供があるだけである」と嘆いているのに、その年若い子供の、よりによって三男が軍事をすべて託されているのは不自然である。
『公卿補任』によれば、高市は当時19歳くらいだったという。
大津は686年に24歳で殺されるので、壬申の乱の672年にはまだ10歳だったはずである。
また、草壁は『書紀』に「大津京で生まれた」とあるから、生まれたのは667年以降であり、4〜5歳といったところ(忍壁も同様)。したがって「高市(19歳)、大津(10歳)、草壁(4〜5歳)」というのが正しい年齢順になる。
当時の19歳は立派な成人であり、総大将だったとしてもおかしくはない。
そのかわり「年若い子供があるだけである」という大海人の言葉は不適切だということになる。
不思議なことがもうひとつある。
大海人の子で、草壁と忍壁は、大海人と共に最初から吉野にいた。
一方、大津と高市は、最初は近江京にあり、大海人の挙兵後、大津は伊勢で、高市は伊賀で大海人軍と合流している。
大海人の息子でありながら、大津と高市はなぜ近江京にいた(いられた)のだろうか。
大津の場合、母の大田が亡くなったあと、まだ子供だったので祖父の天智に引き取られていたと考えられるが、問題は高市である。
高市の母は胸形君徳善の女・尼小娘という地方豪族の娘とされている。
まして天武の長男ならば、最初から天武とともに吉野にいたはずである。
近江京にいられたことの方が不自然なのだ。
『扶桑略記』の最も古い金勝院本には、高市は「天智の三男」とあるらしい。
歴史学者はこれを「天武の三男」の書き間違いとしているが、大津や草壁より下ではありえないことはすでに証明済みだ。
高市が天武ではなく、天智の子だったとすれば、あらゆる疑問が氷解する。
大友は壬申の乱に敗れて自害したとき25歳だから、高市は大友の6歳年下の弟だったのではないか。
『書紀』が高市を天武の子としているのは、息子が父の即位のために戦ったという話にしたかったからである。
しかし、ウソにウソが重なり、長屋親王までも天武の孫だったことになってしまった。
これも、長屋親王が天智の孫だったと考えれば、古代史の多くの謎は謎でなくなってしまうのだ。
高市を天智の子とすると、正しい系図は下のようになる。
(後述するが、鸕野皇女は大田皇女の同母妹ではなさそうである。)
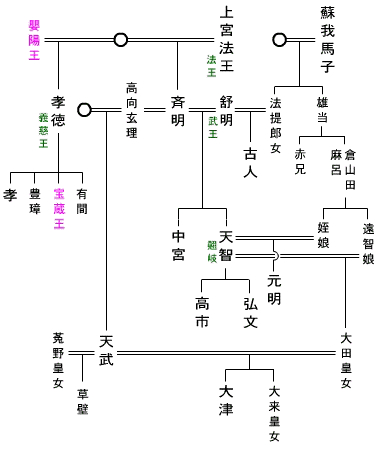
「高市=阿波伎」説
小林惠子氏の新刊『本当は怖ろしい万葉集』には、高市に関する新説がある。
万葉集は倭国語の音を万葉仮名すなわち漢字で表記しているわけだが、あくまでも倭国語だから、古代朝鮮語の発音で読むと無意味な音の連続になって、意味が通じないはずである。
ところが、『もう一つの万葉集』等の著作で知られる李寧煕(イーヨンヒ)氏によれば、舒明、間人、額田、大海人、そして高市らの歌は古代朝鮮語でも読めるという。そのような漢字を選んで作ってあるわけだ。
もちろん、そんなことをすると歌の意味が違ってしまうが、目的はまさにそこにあり、たとえば倭国語の表面上の意味は恋の歌だが、古代朝鮮語で読むと、正史には書かれていない政治裏面史が読み込まれていたりするのだという。ここでは実例は挙げないので、関心のある方はぜひ『本当は怖ろしい万葉集』および李寧煕氏の著作をお読みいただきたい。
しかしよく考えると、大陸から渡って来た作者による歌はもともと朝鮮語で詠まれたのではないか。額田と大海人のように、お互いに口頭で歌を交換したとすればなおさらである。
万葉集の中には全く意味不明の難解な歌があるが、これなどは古代朝鮮語で読んだほうがわかりやすいのだという。
ならば、もともと朝鮮語で詠まれた歌を、大伴家持らが表音文字(漢字)に置き換え、さらに倭国語で無難な内容の歌になるような漢字と取り換えるという順序で、最終的に万葉集に収められているような形になったのではないか。
もちろん、倭国で生まれ育った作者の歌は最初から倭国語だったろう。
それ以外の歌は、家持らによる「翻訳」だったというわけである。
万葉集がのちの古今和歌集などとあまりにも雰囲気が異なるのも、それゆえではなかろうか。
李寧煕氏の研究の注目すべき点は、百済語、新羅語、耽羅語などの方言を指摘していることである。
たとえば、額田の歌には新羅訛りがあり、高市の歌には耽羅訛りがあるという。
耽羅とは、百済王子・翹岐(中大兄)が母とともに流された済州島のことである。
もともと高市は耽羅と深い関係があるとにらんでいた小林氏は、この李寧煕氏の指摘に自信を得て、『書紀』の661年、耽羅から来倭した王子阿波伎を、翹岐と現地の女性との間に生まれた子で、これを高市の正体であると提唱している。
翹岐が耽羅に流されていたのは642年だから、そのときの子は661年には18〜19歳になっている。『公卿補任』が高市を19歳としているは、本当は高市が阿波伎として日本史に登場したときの年齢を伝えているのだとすれば、壬申の乱のときには30歳だったことになる。
私は、大友の母と同様、高市の母も後宮の女官、つまり地方豪族の娘とされているので、もともと両者の立場にさほどの違いはなく、大友が皇太子になったのは、単に大友が年長だったからだろうと考えていた。
しかし高市が長男だったとすると、なぜ大友が即位したのかが改めて問題となる。
唐の劉徳高が中大兄の倭王即位を承認した会談(665年)の際、大友の相を見て称賛したとあることから、大友はそのときに皇太子とされた可能性があるが、大友は倭国で生まれ、倭国で育ったゆえに、皇太子にふさわしいと考えられていたのかもしれない。
つまり朝廷側は、高市をあくまでも耽羅からの客人として扱っていたということである。
しかし、高市が天智の本当の長男ならば、天智のあとをついで倭王になりたがるのは当然で、彼は最初から大友を「政敵」と見なしていたことになるのだ。
十市皇女
井上靖氏の小説にも描かれている古代史のヒロイン・額田女王は、歌人としての類いまれな才能と美貌ゆえ、「兄」の中大兄が「弟」の大海人から半ば強引に奪ったというストーリーになっていて、通説もほとんどそのように語られている。
しかし、額田が中大兄の妃であったという史料はどこにもないらしい。
これは万葉集の歌を表面的に解釈した結果としての憶測が定説化したものにすぎないのだ。
小林氏は、額田を中大兄の異母姉とし、中大兄、間人らと同じ船で耽羅から倭国にやって来たと述べている。
小林氏曰く、百済王・武王は万葉仮名の発明者で、額田は父の文才を受け継いだのではないかというのだ。
額田の出自については「持統」で考察する。
額田が大海人の妻だったことは『書紀』にも記載があり、両者の間に生まれたのが十市皇女である。
壬申の乱のときに、大友妃の十市が、大海人側に鮒の包焼に密書をかくして届けたという『宇治拾遺物語』の記述や、万葉集で両者が交わしている歌から、十市と高市は恋人同士だったと推測できる。
小説でも、兄妹でありながら愛し合う2人が政略結婚によってその仲を引き裂かれるという話になっているが、彼らは兄妹ではなく、正真正銘の恋人同士だったのだ。
十市は政略結婚で皇太子・大友の正妃とされ、高市は一時的に弟に恋人を横取りされた形になった。
しかし、十市は近江朝の様子を大海人に伝えるスパイであった。
大海人から高市、大津への連絡も、十市がメッセンジャーになっていたのだ。
そして高市には、クーデターが首尾よく成功すれば、自分に倭王の座と十市がまとめて転がり込んでくるという甘い期待があったのである。
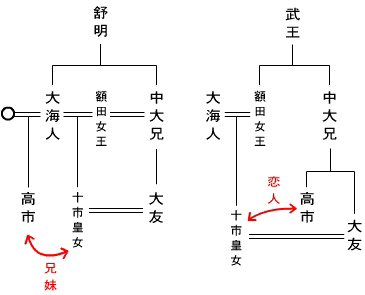
左は通説による系図。右は高市を中大兄の子、額田を中大兄の異母妹とする系図。
壬申の乱
近江を出て、大海人と合流した高市は、大海人に「近江に群臣あろうとも、どうしてわが天皇の霊威に逆らうことができようか」と言っている。
生者に「霊威」という言葉は使わないので、「わが天皇」とは亡父・天智のことを指していると思われる。
「天智の子である自分に近江の群臣が逆らえるわけがない」と言っているわけで、事実その通りになった。
『書紀』に、大伴連吹負(ふけい)が高市になりすまし、わずか数十騎で大和にあった近江勢を降伏させたエピソードがある。朝廷軍が高市の名を聞いただけで戦意を喪失するほど、来倭後の高市に対する朝廷内での評価は高かったようだ。
大海人のもとに馳せ参じたとき、高市は大海人に背をなでてもらっている。これは、豊璋が百済王に即位したとき、鬼室福信の背をなでてねぎらった人物もまた大海人だったことを暗示している。
大海人にとっても、近江京の内情を把握している高市を味方に付ければ戦闘は限りなく有利に展開できる。
大海人は高市に、勝てたらおまえの即位に協力するぞと口約束をし、高市を思うままに操ったのではないだろうか。
壬申の乱は、近江の朝廷軍が吉野の大海人軍を迎え撃つという性質のものだったはずだが、高市が大海人側に寝返ったことで、「高市と大友の兄弟対決」に変わってしまった。大海人もその状況を利用したと見え、壬申の乱の間、美濃の不破の仮宮から一歩も外に出ていない。
思えば、近江朝は、天智を王とする「新生百済王朝」的な性格が強すぎたのではなかろうか。
古い豪族である大伴氏や物部氏、東国の地方豪族らは、それぞれ不満や不安を抱えていたのかもしれない。
そこへ、天智の本当の長男である耽羅王子が現われ、絶妙のタイミングで構造改革を断行すべく立ち上がったものだから、二万の兵を率いて高市側に帰属した尾張国司・少子部連鉏鉤(ちいさこべのむらじさいち)を始め、近江側から吉野側へ寝返るものが続出したのである。
高市側に帰属した兵士たちは、近江軍との区別がつくように、衣服の上に赤いきれを付けていた。
赤は前漢の高祖・劉邦の好んだ色で、漢の皇帝の血筋である大海人のチームカラーだったようだ。
ちなみに劉邦は王族でも貴族でもなく、庶民の出で、いわば豊臣秀吉タイプの英雄だった。
これも武力で革命を成功させた天武に通ずるものがある。
もし天武が天智の弟だったら、自らを劉邦になぞらえるのは不適切である。
672年7月22日 吉野軍は最終決戦地である琵琶湖のほとりの瀬田川の戦いで勝利した。
大友は翌23日に自害したとあるが、物部麻呂に殺された可能性が高い。
近江朝廷の右大臣・中臣連金は惨殺、左大臣・蘇我臣赤兄や大納言巨勢臣人およびその子孫は配流の処罰を受けた。