孝 徳 |
|||||||
孝 徳
ねこ: としちん: ねこ: としちん: ねこ: としちん: ねこ: としちん: |
高向王
今まで見てきたように、春日山田皇女や推古は複数の大王の代にわたって后であったが、『書紀』が書かれた8世紀は女性の再婚を罪とする儒教の影響で、大王家のそのような騎馬民族的風習の歴史は抹消され、それぞれの大王の后は別名で記されている。堅塩媛が敏達と再婚して生んだ子も、全て欽明との間に生まれたことになっている。
ところが、なぜか宝皇女は舒明とは再婚だったことが暴露されている。
初め用明天皇の孫高向王(たかむこおう)に嫁して、漢皇子(あやのみこ)を生まれた。
後に舒明天皇に嫁して、二男一女(天智天皇・間人皇女・天武天皇)を生まれた。
『書紀』の中で、高向王と漢皇子に関する記述はこれだけである。
宝皇女にとって名誉とは言えない経歴ゆえ、さほど重要でない人物との結婚だったのであれば歴史から抹消されてもおかしくないはずだが、この記述にはどのような意味があったのか。
小林惠子説を参考に、まず高向王について調べてみよう。
『新撰姓氏録』には応神天皇時代に七姓の漢人が帰化したとあり、その筆頭に高向村主(すぐり)と高向史(ふびと)が挙げられている。
応神は高向村主を阿智王と名のらせ、高市郡檜隈(たけちぐんひのくま)に居住地を与えたという。
阿智王の系図のひとつ『大蔵系図』によると、阿智王は後漢帝の子孫。
後漢献帝〜石秋王〜○〜阿智王〜阿多部王と連なる。
阿多部王は高貴王と号し、初めて来日して準大臣になり、茅渟王の娘と結婚して坂上、大蔵、蔵内の三子をなしたという。
『大蔵系図』の傍系の『秋月系図』には、高貴王は大臣に任じられ、妻は斉明天皇だったとある。
『書紀』に斉明の最初の夫とある「高向王」とは、高貴王のことではないか。
そして、高向姓の高官と言えば、孝徳朝で国政の顧問である国博士に任命された高向玄理がいる。
彼は「高向史玄理」ともいうので、高向史の一族に間違いない。
高貴王 = 高向王 = 高向玄理
たしかに「茅渟王の娘と結婚」「妻は斉明天皇」などの記事があるが、この真偽についてはのちほど考察する。
漢皇子
天智と天武は、共に父は舒明、母は斉明で、天智の方が兄であるというのが正史によって確定された史実である。
しかし「本当の史実」は、天武は622年生まれ、天智は626年生まれ。
ゆえに天武の方が4歳年上であるというのが私の結論である。
天智は、日本書紀に「東宮の開別皇子は舒明13年に16歳(数え年)で誄をよまれた」とあり、626年という誕生年が導かれる。
一方、天武の誕生年がわかる記述は書紀にはなく、鎌倉時代の『一代要記』、南北朝時代の『本朝皇胤紹運録』などに、天武は65歳で死去したとあり、没年から622年誕生と推定できる。
ただし『一代要記』では天智の誕生年が619年、『本朝皇胤紹運録』では614年にそれぞれ引き上げられ、あくまでも天智・天武の兄弟順は変えないようにしてある。
その逆パターン、つまり天智626年誕生という書紀の内容を尊重し、天武の誕生年をそれ以降に設定したものは全くないので、「天武622年誕生」がいかに信頼性の高いデータとして鎌倉〜室町時代まで保存されていたかを物語っている。それは正史の記述をくつがえす内容だったからこそ、その時代まで公表されなかったと考えるべきだろう。
しかし、ようやく天武の誕生年についての真実が語られる時代になっても、天智・天武の兄弟順はすでに史実として確定されており、中世の歴史家たちもさすがに国家権力には刃向かえず、やむなく天智の誕生年を操作せざるをえなかったのだろう。
天智の誕生年を操作することに関しては幕府も朝廷も黙認しているので、とにかくタテマエとして重要だったのは「天智が兄、天武が弟」という兄弟順であり、そのとき、それぞれの著者がそれぞれの判断で、天武の622年より早い年を適当に選んだために、史料によって天智の誕生年がバラバラになってしまったと考えられる。
天武は天智の同母弟というのが政府のタテマエだが、天武の方が年上だったことを知る人たちに対しても、書紀は天武即位の正当性を納得させる必要があった。
そこで、天武が実は斉明の連れ子で、天智の異父兄だったと解釈できるように挿入されたのが漢皇子に関する記述であり、天武の方が年上だったことを知っている読者に、漢皇子=天武であると「読ませるように」書かれたのだと私は思う。
したがって、ここで安易に「天武は天智の異父兄だったのか」と思ってしまっては書紀の思うツボであり、「天智の同母弟」と同様、「天智の異父兄」というのも政府のタテマエであって、そのまま信用してはいけないのである。
井沢元彦氏は、漢皇子の父親が高向王とされていることから、天武は皇位継承権を持たなかったために壬申の乱というクーデターによって王権を簒奪したのではないかと論じている。
しかし、書紀が漢皇子=天武であると「読ませるように」書かれているならば、父親が高向王であることが天武の即位を妨げる要素であってはならず、クーデターが必要だった本当の理由は、天武の母が「斉明ではなかった」ことの方にあったと考えるべきである。そして、このことにより、当時は父親が必ずしも大王である必要はなく、即位の条件は「斉明の血筋」にあったことを書紀ははからずも暴露しているのである。
天武が天智に娘たちを4人も差し出させているのも、斉明の血筋である天智の娘に子どもを生ませれば皇位継承権が発生するからにほかならない。天武は、その時点では自分の息子世代に即位の望みをつないでいたわけだ。天武自身が斉明の子ならそんなことをする必要はなかったはずであり、斉明の子ではなかったからこそ『記紀』の編纂を命じ、その中で自らを「斉明の子」と確定させ、即位を正当化する必要があったのだ。
また、天武は皇位継承権こそなかったが、天智から娘を4人差し出させるだけの実力者であったという事実は押えておきたい。
天武は天智より年上で、両者は赤の他人であった。
当時は斉明の血筋(天智系)であることが皇位継承の条件であり、斉明の子でない天武は武力(壬申の乱)によって王権を簒奪せざるをえなかった。
即位後の天武は、自ら編纂を命じた『日本書紀』の中で「天智の同母弟」あるいは「天智の異父兄」になりすましている。
天武が新王朝の祖であることを宣言しなかったのは、自分のあとをつぐべき息子たちがちゃんと天智の娘を母に持っていたからであり、あくまでも斉明の血筋が重視されていたのである。
記紀の天皇系譜は、天照大神を祖神とする天皇家が日本の統治権を世襲することを正当化するための創作であり、斉明が初代神武から続く天皇家の末裔であったと信じる必要はない。
むしろ、斉明が最初に即位したとされるときの「皇極」という、ほとんど「初代」という意味にも読み取れる諡号に注目すべきであろう。
天武が定めた「八色の姓」という制度がある。
天皇一族の地位を高めるため、旧来の臣・連の中から、皇族と関係の深い者に真人・朝臣・宿禰の姓を与えるもので、継体や舒明の子孫、そして天武自身とその息子たちには最高位の「真人」という姓が与えられている。
ところが、まぎれもなく斉明の血筋である天智系の男子には真人姓が与えられていない。
ここで注意すべき点は、真人姓を授与する側の立場にあったのは天武であり、彼とその息子たちは、あくまでも自己申告で真人姓を名乗っているにすぎないということだ。
真人姓は必ずしも継体や舒明の子孫だったことを証明するものではなく、むしろ彼らは継体や舒明の子孫を「名乗りたいがために」、わざわざ八色の姓を制定したと考えるべきである。
そして、八色の姓のもうひとつの目的は、天智系の男子に真人姓を与えないことで、皇位継承権を天武の子孫が独占することだったのである。
高向玄理
608年 小野妹子の遣隋使のとき、高向玄理は医者の恵日、倭漢直福因らと共に留学生として隋に渡り、現地で隋から唐への歴史的な政変を体験して、640年にようやく帰国したとされている。
そして645年の大化の改新で国博士に任じられ、654年の遣唐使に参加。
660年、唐の地で永眠したという。
推古31年(622年) 新羅と任那の使者が来朝し、仏像・金塔・舎利をたてまつった。
仏像は蜂岡寺に、他の金塔・舎利などは四天王寺に納めたという。
蜂岡寺はのちの広隆寺だから、このときの仏像が国宝の弥勒菩薩像であり、彼らは上宮法王(聖徳太子)の葬礼のためにやって来たと考えられる。
その新羅使者に従って、唐の学問僧の恵斉・恵光らが来倭。
当時の学問僧は、政治的な目的を持った外交官でもあった。
すでに述べたように、唐は馬子の上宮法王暗殺の影で黒幕的役割を果たしていた疑いがあり、新羅の弔問に合わせてやって来た彼らは、一気に倭国への内政干渉を開始したと考えられる。
高向玄理と共に隋・唐で学んだ恵日、福因もこのとき一緒に帰国している。
彼らに対して、現代人の感覚のままに「留学生」という言葉を用いるべきではないだろう。
当時の唐と倭国では、あらゆる意味で、終戦直後のアメリカと日本ぐらいの差があったはずだ。
福因らは唐によって、ある意味「洗脳」され、今後の列島支配を有利に運ぶために教育されたに違いない。
その中でも「エリート」的な存在が玄理であった。
私は、玄理もこのとき帰国していたに違いないと思う。
彼が640年まで帰国しなかったかのように書かれているのは、622年生まれの天武の父親ではないというアリバイ工作のためだったのではないか。
山背が即位したあとの632年、唐から高表仁が来倭している。この高表仁が帰国する際、見送った中に「黒麻呂」という人物がいるが、玄理のことだと思う。唐からの正式な使者を接待する役目として、玄理ほどの適任者はいない。
問題は、福因らの帰国が『書紀』には622年7月とあり、このとき玄理が一緒に帰国したとしても、それから作った子どもだと622年のうちに生まれることはまず不可能だということである。
天武は、玄理が唐で現地の女性との間に作った子で、0歳児もしくは母親のお腹の中に入ったまま来倭したのかもしれない。
つまり、玄理は後漢献帝の子孫であるが、天武は母親も中国人だった可能性があるのだ。まさに「漢皇子」である。
そして倭国では玄理側の氏族によって養育され、最初に覚えた言語は日本語だったとすれば、万葉集にあれだけ流暢な歌が残っているのも不思議なことではない。
宝皇女
ちなみに、『大蔵系図』の「阿多部王は高貴王と号し、初めて来日して準大臣になり・・・」の、「初めて来日して」を重視するならば、玄理は倭国から中国に渡った留学生ではなく、もともと大陸の生まれで、622年に初めて列島の土を踏んだ可能性もある。
いずれにせよ、玄理は大陸と列島を往き来した国際政治家であり、根拠は後述するが、彼は630年までに、唐が栄留王を冊立していた高句麗に渡り、東部大対廬(だいたいろう)という役職を与えられたと考えられる。
そこで玄理は、宝皇女と運命的な出会いをする。
かつて西突厥可汗・達頭は、隋との戦いで東へ東へと追いつめられ、同じく隋と敵対する高句麗と連合。
そのとき、騎馬民族の風習に従い、妻と娘を嬰陽王に差し出したようだ。
その「娘」こそ宝皇女だったのである。
そして「妻」は嬰陽王との間に男の子を儲けた。これが軽皇子(孝徳)である。
私は、ここで「宝皇女と高向王の結婚」が成立したのだと考えていたが、それは天武の母親をどうしても宝皇女にしたい『書紀』の方便だったと考えたとき、彼らが実際に結婚していたと考える必要はない。
では、玄理は宝皇女とどのように関わったのだろうか。
玄理の次なる使命は百済の武王を懐柔し、唐の勢力圏内に収めることだった。
武王は、前百済王の法王(達頭、上宮法王)から譲位された人物だったので、基本的には反唐であった。
「山背」の条で述べたように、武王は法王と蘇我氏の両方に義理があった人物で、すでに馬子の娘・田眼皇女(私見では古人大兄の母・法提郎媛と同一人物)が后になっていたと思う。
しかし、さすがに法王の娘を差し出されたらこれは決定的だろう。
しかも宝皇女は、のちに蘇我入鹿を骨抜きにしているようにペルシア系の絶世の美女であったと私は想像している。
この政略結婚の「仲人」が玄理だったのである。
武王の后の座はあっけなく宝皇女に移り、武王もその政策を転換し、親唐へと転じていく。宝皇女が舒明の皇后になったとある630年がその年であろう。
これは蘇我氏にとっては大ダメージだから、やはり玄理は当時の倭国のためではなく、唐の手先として暗躍した人物だったのである。
蓋蘇文
玄理は632年には倭国で高表仁の接待をしているから、何度も大陸と列島を往き来したようだ。
高句麗時代は、息子の漢皇子も彼の手元にあり、英才教育を施されたと思う。
630年当時、漢皇子は9歳。
私の想像通り、宝皇女が絶世の美女だったとするならば、漢皇子にとっても「きれいなお姉さん」として強く印象付けられていたかもしれない。もちろん当時は、将来お互いの運命を握り合う者同士になろうとは夢にも思わなかっただろう。
小説チックな想像をすれば、もし少年が宝皇女に淡い恋心を寄せていたとすれば、彼女が政略結婚で百済に連れて行かれたときの悲しさと、そのときの父への恨みが、その後の彼の人生を決定したのかもしれない。
また、この時代の高句麗は、完全に唐に服従していたわけではなかった。
栄留王自身、唐に即位させてもらった義理で親唐政策をとってはいたが、国内には嬰陽王時代の家臣など、反唐派も根強く存在していた。
自分のような立派な国際政治家に育ってほしいという父の願いとは裏腹に、漢皇子は成長とともに武将としての風格を備え、いつしか反唐派の期待の星として成長していく。
641年、クーデターを敢行し、栄留王を殺して傀儡の宝蔵王を立て、高句麗を専断した蓋蘇文(がいそぶん)こそ、20歳の漢皇子だったと思われる。
(玄理が高句麗の東部大対廬だったという推理は、実は蓋蘇文の父が東部大対廬だったと言われているから。)
蓋蘇文のフルネームは、淵蓋蘇文(えんがいそぶん)という。
しかし中国の史書では、唐の高祖・李淵と同じ「淵」の字を用いるのをはばかり、泉蓋蘇文(せんがいそぶん)、あるいは蓋金(こうきん)と書かれている。
「古人」の条でも紹介したが、百済と高句麗の政変を伝える『書紀』の記述に、高句麗の使人が難波津にやってきて「去年(641)の6月、弟王子が亡くなり、秋9月、大臣伊梨柯須弥(いりかすみ)が、大王を殺し、弟王子の子を王とした」と伝えたとある。
淵蓋蘇文は当時の高句麗では「イリ・ガ・ス・ム」と発音され、この発音に忠実に「伊梨・柯・須・弥(イリ・カ・ス・ミ)」と記録されているわけである。
淵蓋蘇文は、「淵」が姓で「蓋蘇文」が名である。
唐での別名「蓋金」から「蓋」を姓、「蘇文」を名と考える人もいるが、これは間違いで、『聖徳太子伝暦』には「入霞」という字が当てられていることからも、イリ+カスミが正解である。
蓋蘇文というファーストネームだけで書かれることが多いのは、やはり「淵」という名字がずうずうしいと考えられたという理由が大きいのだろうが、日本の天皇家に姓がないのも、もしかしたら蓋蘇文が姓を捨て去ったことに由来するのではないか、などと私は妄想している。
664年(天智3年)、高麗の大臣「蓋金」が死んだとして、子どもたちへの遺言が記されている。
蓋蘇文のことを伝えているのは朝鮮の『三国史記』、中国の『旧唐書』『唐書』『資治通鑑』などだが、遺言の記事があるのは『書紀』だけである点が注目される。
外国の史料では蓋蘇文の没年は666年とされ、高句麗はそのわずか2年後に唐に滅ぼされたことになっている。
『書紀』とは没年に2年のズレがあるが、いずれにしても、天武=蓋蘇文ならば、「死んだ」と称して列島に渡り、死んではいなかったことになる。
このときに蓋金が死んだという『書紀』の記述を尊重し、天武=蓋蘇文ではなく、天武=金多遂説を唱える研究者もあるが、天武と新羅の関係はむしろ天武の妻たちに新羅人が多かったことに由来すると私は考えている。
私は「天武=蓋蘇文」説を前提に話を進めていきたい。
642年に難波津にやってきた高句麗の使人の言葉に戻ろう。
弟王子とは、栄留王の弟とされる太陽王のことだが、嬰陽王と同じ「陽」の字がつくところから、実は嬰陽王の子、すなわち軽皇子のことではないかと小林惠子氏は推理している。
太陽王が倭国に亡命して軽皇子となり、さらに百済に渡って義慈王となった641年をもって、太陽王は死んだとされたのだ。
したがって蓋蘇文が立てた宝蔵王とは、義慈王の子だったのである。
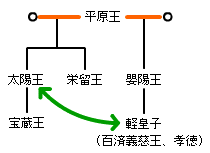
[ 高句麗王の系図 ]
太陽王とは栄留王の弟ではなく、軽皇子のことか?
641年の蓋蘇文のクーデターをきっかけに、668年に唐が高句麗が滅ぼすまで、両国の敵対関係は続く。
蓋蘇文は生涯にわたって唐に命を狙われることになるということを覚えておいていただきたい。
百済の武王が亡くなり、義慈王が即位したのが高句麗のクーデターと同じ641年だったのはけっして偶然ではない。
蓋蘇文はその修行時代、父の玄理に同行して百済や新羅を訪問し、義慈王になる前の軽皇子にも会っていたと思う。
軽皇子は、あの美しい宝皇女の異父弟である。
かつて父の玄理が仕えたこともある上宮法王のカリスマ性や、唐に対する敵がい心を蓋蘇文に植え付けた張本人は軽皇子だったのかもしれない。
このように、早い時期から反唐の嬰陽王の血筋(義慈王、宝蔵王)と軍事力(蓋蘇文)は共謀していて、玄理によって親唐派に転じていた武王が死んだとき、かねてからの計画を実行に移したのではなかろうか。
自らを漢の高祖にも、また上宮法王にもなぞらえていた蓋蘇文は、あとは蘇我氏さえ滅ぼせば自分が倭王になれるものと確信していたのかもしれない。
しかし、一方の義慈王は、蓋蘇文のことを「有能な軍将」という以上には考えていなかった。
また、蓋蘇文の前に立ちはだかった最大の壁は、彼自身に上宮法王の血が流れていなかったという、血統の問題であった。
「将軍」
643年、山背が入鹿軍に急襲されて生駒山に脱出したあとのことを、『書紀』は次のように記している。
| 上宮の王らをはるかに山中に見た人があった。帰って入鹿臣に伝えた。入鹿は聞いて大いに恐れた。 さっそく軍隊をおこし、王のありかを高向臣国押に告げて「速やかに山に行ってかの王を探し捕えよ」といった。国押は答えて、「私は天皇の宮をお守りすべきですから、外には出られません」といった。 そこで入鹿が自分で出かけようとすると、古人が「鼠は穴に隠れて生きるもの、穴を失えば死なねばならぬ」と助言し、入鹿は行くことをやめ、将軍たちを送って生駒山を探させた。 山背らは山を降り、再び斑鳩寺に入った。やがて兵に取り囲まれ、三輪文屋を通じて「我々は自決する」という内容を将軍に伝え、そこで亡くなった。 おりから大空に五色の幡や絹笠が現われ、さなざまな舞楽とともに空に照り輝き寺の上に垂れかかった。多くの人がそれを入鹿に指し示したが、入鹿が見たとき、幡や絹笠は黒い雲に変わっていた。 |
ここには高向臣国押という高向姓の人物と、将軍という人物が登場する。
「私は天皇の宮をお守りすべきですから、外には出られません」と答えた高向臣国押は、入鹿が死んだときにも戦いを放棄して逃げた様子が『書紀』にあり、その後二度と姿を見せていない。
高向臣国押とは高向玄理のことだと思う。
高句麗に宝蔵王が即位し、親唐派の玄理の居場所がなくなれば、彼は倭国に戻るしかなかったはずだからである。
しかしあくまでも平和主義者だった彼は、戦争になるといつも逃げてばかりいたようだ。
将軍とは、一般には巨勢徳陀のことと考えられているが、『書紀』は巨勢徳陀のときはちゃんと「巨勢徳陀将軍」と記しているので、単に「将軍」とあるときは名前を伏せなければならない人物であり、ここでは蓋蘇文を意味していると考えられる。
高向臣国押をわざわざ登場させているのも、彼が蓋蘇文の父だからであり、父と子を対照的に描いているのだ。
647年から662年までの間、『高句麗本紀』には蓋蘇文に関する記載がない。
その頃、蓋蘇文は倭国に渡ってイリカスミと呼ばれ、『書紀』には、中大兄らとともに難波京から飛鳥へ移る653年、初めて大海人皇子の名で登場する。
しかしすでに考察したように、643年の山背殺害事件にも、おそらく645年の乙巳の変にも、クーデターのプロである蓋蘇文はすでに関与していた。『書紀』に「大空に五色の幡や絹笠が現われ」とある「大空」は、「大海人」と対をなす言葉である。
京都の泉涌寺では天智が初代天皇とされ、次はいきなり光仁天皇(天智の孫。平安京に遷都した桓武天皇の父)になっている。その間の天武〜持統〜文武〜元明〜元正〜聖武〜孝謙〜淳仁〜称徳(孝謙の重祚)天皇は、いわば「無縁仏」になっているのだ。
天智系天皇家が正統とされる真の理由は、それが上宮法王の血筋だからというのが私の主張である。
『書紀』では天武を天智の同母弟としているが、兄と弟が逆だったというだけの話なら上宮法王の孫であることには変わらず、無縁仏にされているのはおかしい。
天武が宝皇女の血筋にこだわったのは、宝皇女が上宮法王の娘であり、それが当時の倭国における皇位継承の条件だったからなのである。
孝徳即位
下は、孝徳即位に関する書記の記述の要約である。
入鹿を斬った中大兄らは法興寺にこもり、入鹿の屍を蝦夷に送り届けさせた。 その翌日、天皇は位を中大兄に伝えようとした。 中大兄を皇太子、阿倍内麻呂を左大臣、蘇我倉山田麻呂を右大臣、中臣鎌足を内臣、僧旻と高向玄理を国博士とした。 |
蓋蘇文は、倭国における義慈王主導の一連のクーデターを成功に導いた。
乙巳の変で入鹿を殺した実行犯も、ボンボン育ちの翹岐ではなく、本当は蓋蘇文だったのかもしれない。
義慈王は蘇我氏へのリベンジを果たしたあと、自ら孝徳として即位している。
たしかに、彼の蘇我氏への復讐劇は、軽皇子時代、上宮法王によって次期倭王候補とされながら、馬子が上宮法王を暗殺し、馬子の子・山背に横取りされてしまったことが発端であった。
しかし、すでに百済王となり、祖国の高句麗も息子にまかせている今、倭国には甥っ子の中大兄を立てれば十分であろう。
義慈王自身もそのつもりだったと私は思う。
一方、蓋蘇文にしてみれば、それまで義慈王に協力してきたのは全て自分が倭王になるためだった。
蓋蘇文は、中大兄を即位させようとする智積に猛然と噛み付いたと思われる。
智積は、上宮法王の実の孫である中大兄を差し置いて蓋蘇文を即位させる道理はないとこれを却下したが、このために命をかけてきた蓋蘇文は簡単には引き下がらなかった。
やむをえず、智積は百済から義慈王を呼び寄せ、義慈王が暫定的に百済王と倭王を兼任する形で話をつけたのだと思う。
さすがの蓋蘇文も、まだ面と向かって義慈王に盾突くことはできなかったようである。
『書紀』には、鎌足が中大兄を説得し、「叔父上を立てて」孝徳を即位させたとあるが、智積が中大兄以上に説得しなければならなかった相手は蓋蘇文だったのである。
孝徳が中大兄の妹の間人を倭国における正妃としたことは、蓋蘇文にさらなる疎外感を抱かせたことだろう。
孝徳が蓋蘇文の父・高向玄理に国博士というポストを与えたのは、孝徳なりに蓋蘇文に気を使ってのことだったのかもしれない。本来ならば、反唐色の強い孝徳朝に、玄理のような人物は不要だったはずだからである。
もっとも、敵に回したくないから抱え込んでしまおうという意図だったのかもしれないが。
古人の死と倭姫王
乙巳の変によってプレッシャーをかけられた古人大王は、中大兄に娘の倭姫王を差し出し、頭を丸めて出家してしまった。その時点では彼も、このあと倭王になるのは中大兄だと考えていたのだろう。
この話は、同じ『書紀』の、26年後の671年、病床の天智が大海人を呼び、後事をお前に任せたいと言ったときに、大海人が「どうか大業は皇后にお授け下さい。そして大友皇子に諸政をおまかせください」と言って固辞し、頭をまるめて吉野へ出家したという話に酷似している。
おそらく大海人の話の方がフィクションで、古人の行動をモチーフにしたものと思われる。
「どうか大業は皇后にお授け下さい」という大海人のセリフの「皇后」こそ、古人の娘・倭姫王であるが、のちの歴史において、元明女帝の娘だった元正を除き、女帝は全て皇后経験者で、父が大王だった女性に限られている。これが『書紀』が書かれた時代の「女帝の条件」だったとすれば、古人はたしかに大王だったことになる。
また、上宮法王〜山背〜古人が実際の大王の系譜であったとするならば、推古朝と皇極朝は存在せず、ヒミコやトヨの時代を除き、我が国最初の女帝は斉明だったことになる。
斉明が即位した理由は後述するが、孝徳が即位したときと似たような理由であり、やはり大海人がからんでいた。
女帝というシステムは、大海人が原因で生まれたとさえ言えるのである。
それをふまえて『書紀』を読むと、「どうか大業は皇后にお授け下さい」という大海人のセリフも、意味深く感じられるというものである。
645年9月、古人は謀反を企てたとして中大兄が派遣した兵士たちに殺害された。
しかし中大兄に嫁いだ古人の娘・倭姫王が、父を殺されたうらみを中大兄に抱いた形跡がないことから、これも次に述べる倉山田麻呂事件同様、黒幕が別にいると考えられる。
倉山田麻呂事件
649年、わずか1週間のうちに、大化の改新で就任した左右大臣が相次いで亡くなった。
阿倍内麻呂は、孝徳の軽皇子時代の妻だった小足媛の父で、有間皇子の祖父。
一方、蘇我倉山田麻呂は中大兄妃・造媛(みやつこひめ)の父。
つまり両者は、それぞれ孝徳と中大兄の舅だったことになる。
倉山田麻呂は石川麻呂ともいい、かつて蘇我氏の中で唯一、軽皇子派だった人物。だからこそ彼だけは大臣になれたのだった。
彼らは、新しい冠制に従わないなど、孝徳朝の改革に反抗的だったため、改革急進派の中大兄皇子に殺されたというのが通説になっている。下は書記の要約である。
孝徳朝は647年に七種十三階の冠位を制定し、翌年には古い冠制が廃止されたが、左右両大臣はなお古冠を用いた。 3月17日、左大臣の阿倍内麻呂が薨去。 24日、中大兄皇子は、右大臣の蘇我倉山田麻呂の異母弟・日向(ひむか)から、倉山田麻呂が自分を殺そうとしているという密告を受ける。 大臣の資財を没収すると、すぐれた書物には「皇太子の書」、重宝の上には「皇太子の物」と記してあった。 4月、左大臣に巨勢徳陀、右大臣に大伴長徳が就任。 |

倉山田麻呂は、石川麻呂ともいう。
倉山田麻呂は中大兄の謀略によって自殺に追い込まれ、造媛もそのショックで狂い死んだとされ、ひたすら権力を追及する中大兄の血も涙もない残忍な性格を示す代表的なエピソードになっている。
しかし、中大兄の暗殺計画に関する密告を、中大兄自身が孝徳に報告している部分など、いかにも不自然である。
倉山田麻呂の資財に中大兄の名前が記されていたというのは、かつて上宮法王の忠臣だった彼が、上宮法王の孫の中大兄を支援していた事実を物語っている。しかし、倉山田麻呂が死ぬまで、中大兄がそのことに気付かなかったとは考えにくい。
すでに見てきたように、大化の改新の主導者は孝徳(義慈王)であった。
山背、蝦夷・入鹿父子、古人など、蘇我氏の主要人物を次々に滅ぼした黒幕であった孝徳の魔の手が、ついに倉山田麻呂にまで及んだ事件だったと考えるべきであろう。
古人の殺害と同様、この事件でも中大兄は完全に蚊帳の外で、名前を利用されただけだったのだ。
山背殺害の罪が入鹿ひとりに着せられたように、この事件は倉山田麻呂の冤罪事件であると同時に、中大兄の冤罪事件でもあったのである。
金春秋
いくら孝徳にとって左右大臣がジャマだったとは言え、1週間のうちに2人とも殺すというのはあまりにも強引である。
しかし海外に目を向ければ、649年、唐と新羅が連合し、百済への侵攻を始めている。
孝徳=義慈王ゆえに、彼は早急に百済に戻らなければならなかったのだ。
自分が留守中の倭国を守らせるため、急きょ側近の巨勢徳陀と大伴長徳を左右大臣に付け、阿倍内麻呂と倉山田麻呂がそれを不服としたために、カッとなって殺してしまったというのが真相ではなかろうか。
唐の百済への侵攻のきっかけを作ったのは、誰あろう、孝徳によって国博士に任命された高向玄理だった可能性が高い。
彼はまず新羅を訪問し、次期国王と目されていた実力者・金春秋と会談し、来倭の約束を取り付けた。
翌647年、金春秋が来倭し、倭国と新羅は一時的に国交を回復する。
同じ647年、唐の太宗は2度の高句麗征伐を行ない、いずれも高句麗の抵抗にあって失敗した。
翌648年、金春秋が唐を訪問。
高句麗を倒すためには新羅との連携を強化する必要があると痛感していた太宗は、金を厚遇した。
金も、新羅の制度を中華風にしたいと申し出、太宗より衣服を賜り、のちに本当に唐の衣冠制に改めてしまう。
このとき金は太宗に、百済の義慈王が倭国まで専断しているという玄理からの情報を伝えたと思われる。
その結果、唐は作戦を変更し、まずは新羅と連合して、百済への侵攻を開始したと考えられるのだ。
唐の手先である玄理は、とにかく唐との国交を正常化するために、孝徳を倭国から撤退させたい一心で、金春秋をメッセンジャーとして利用したのだった。
一方、息子の大海人は、あくまでも自分が倭王になる野望を捨てておらず、孝徳を追い出すという点において玄理と利害が一致し、ここは父の外交手腕に期待したというところであろう。
『百済本紀』には、645年5月〜649年8月の義慈王に関する記述がない。
これは義慈王が645年6月に倭国に渡って孝徳になり、649年8月までに百済に戻ったことを意味している。
2017/06/09 改訂