敏 達 |
|||||||
敏 達
ねこ: としちん: |
敏達の正体
敏達が皇太子になったのは欽明条では欽明15年(554年)、ところが敏達条では欽明29年(568年)になっている。
天皇家のオフィシャルな歴史書である『書紀』に、このような矛盾があるのはなぜか。
554年は聖王が戦死した年である。
『書紀』は敏達の正体を、聖王の後継者で、557年に即位した威徳王であると暗示しているのだ。
敏達が「百済」の大井に宮を作ったという記述でも、敏達が百済王だったことをほのめかしている。
欽明条に、彼はすでに百済王子・余昌として登場している。
百済から倭国への援軍要請の記事のあと、553年、彼は兵を挙げて高句麗に進軍した。
余昌は、夜営中に高句麗軍に発見されるが、高句麗軍の将は余昌を「客人」と呼び、実に礼儀正しい応対をした。
余昌は「姓は高麗と同姓の扶余、位は杆率(かんそつ)、年は29」と答え、そのあと、この高句麗軍と戦って圧勝したという。
実に不可解な記述である。
倭国への援軍要請なのに、なぜ百済王子が出兵したのか。
高句麗軍将の、余昌への態度が丁重だったのはなぜか。
なぜ余昌の姓が「高麗と同姓の扶余」なのか。
このようなやりとりのあと、それでも戦いになったのはなぜか。
この話は、余昌の出自が高句麗の王家であり、倭国に亡命していた人物だと考えたときに初めて理解可能となる。
『書紀』は、545年の高句麗の大乱について事細かに記している。
高句麗・安原王の後継者をめぐる外戚同士の戦いで、陽原王が即位するのだが、このとき敗れた対立候補こそ余昌だったのだ。553年に29歳だったとすれば、このときは21歳だった計算になる。
つまり、彼は高句麗王子だったわけだが、のちの威徳王ゆえ、『書紀』には「百済王子」と書かれているのだ。
かつて宣化をサポートした稲目が、今度は高句麗の亡命王子・余昌の後ろ盾となったのである。
稲目の思惑
ここで、全章で紹介した表をもう一度ご覧いただきたい。
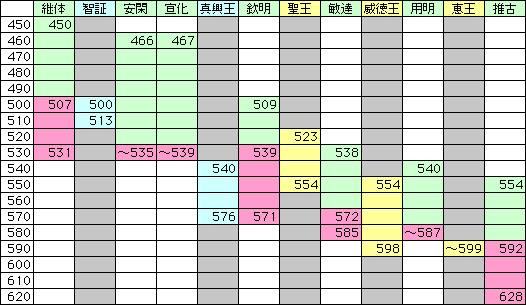
宣化の実際の生年は504年であることはすでにお話しした通り。
欽明は509年に生まれ、523年に百済王・聖王となり、554年に戦死した。
聖王はまだ45歳、戦争による不慮の死だったから、正式なあとつぎは決めていなかったのだろう。
聖王の正妃には、稲目の娘の堅塩媛がおさまっている。
堅塩媛の子と言えば、『書紀』では用明と推古。
推古が生まれたのは聖王の死と同じ554年で、まさに最晩年の子だった。
稲目は聖王にかわって倭王を代行していたわけだが、その聖王が45歳の若さで戦死したことが蘇我氏の列島専断へとつながっていく。
まず手始めに、自分が手塩にかけた余昌を新しい百済王として送り込んだ。
まだ生まれたばかりのプリンセス・推古の、未来の夫でもある。
一方、用明は、自分が百済王になれないとなると、外祖父の稲目を引退させ、自分が倭王を引き継ぐしかないと考えた。
555年2月、百済王子・恵が聖王の戦死を知らせるためにやって来る。
『百済本紀』の598年、威徳王の次に即位したとされる百済王の名が恵王である。
『書紀』に「余昌の弟」とあるのは、即位順が威徳王のあとだからで、実際は義兄であった。
恵王 = 用明
恵王と用明は、即位してすぐに病死したとされている点が共通している。
しかし両者の即位年と没年にはズレがあり、恵王=用明ならば、『百済本紀』の恵王即位の記事の方がウソだということになる。そのようなウソを書いた理由については、のちほど考察する。
『書紀』では、「日本に留まることを望むか」という許勢臣の問いに、恵は「願わくば父の仇を報いたいので、そのための武器を賜りたい。私の去就については天皇の命に従う」と答える。
そのあと稲目が登場し、恵にわけのわからない説教をする。
そして恵は翌年の1月に帰国を願い出、護衛に護られながら百済へ戻る。
ここでの「天皇」とは欽明のはずだが、かわりに出てくるのが稲目である。
欽明=聖王であり、倭国の最高責任者は稲目だったのだから当然である。
しかし、恵はまだ14歳。当時の14歳はりっぱな大人とは言え、百戦錬磨の稲目から見ればまだまだヒヨコである。
それに、稲目は自分のあとを息子の馬子につがせたいと思うようになっていた。
馬子は堅塩媛の兄で、恵の伯父にあたる。
稲目は政治、経済、外交の全てに明るい人間であり、倭国が進むべき独立国家としての道をはっきりと思い描いていたのではないか。
百済にいればいつまでたっても百済王家の家臣にすぎないが、倭国が独立すれば、蘇我氏が文字通り一国一城の主になれる。息子の馬子が、名実ともに倭国の大王として君臨することになるのだ。
稲目は、恵を百済に追い返してしまった。
のちに馬子が大王のとき、どうしても恵=用明に譲位せざるをえない状況に追い込まれるのだが、まだそれは先の話。
突厥からの使者
余昌が威徳王になった2年後の559年、高句麗の陽原王が亡くなり、長子の平原王が即位する。
かつて陽原王との王位決定戦に敗れ、倭国に亡命していた余昌=威徳王にとって、これは母国の高句麗に返り咲くチャンスだった。
ところがそうならなかったのは、高句麗が隋に対抗するために東突厥と連合していたからである。
高句麗だけならまだしも、東突厥と連合されては、とても百済がかなう相手ではない。
突厥という軍事国家が誕生したのは552年、そして中国の史書に「西突厥」という言葉が現れるのは583年だが、もともと突厥は複数の可汗による連合国家であり、かなり初期の段階で東西に分裂していたようである。
高句麗への復帰がかなわなかった威徳王に、さらなる試練が続く。
562年、ついに新羅が加羅を併合(任那の滅亡)。
571年、威徳王の後ろ盾だった蘇我稲目が死去。
この機に乗じて、かつて倭王(宣化)だった新羅の真興王が、本格的に列島奪還に乗り出した。
威徳王は新羅軍を倭国で迎撃すべく、西突厥可汗・達頭(タルドウ)に援軍を要請した。
東突厥は高句麗と連合しているから、百済は西突厥に助けを求めるというのはなんだか安易な発想のようだが、突厥軍が新羅の侵攻に対して倭国の国防に当たること自体はそれほど特別なことではない。なぜなら、4〜5世紀に列島に渡来した秦氏もテュルク系であった。
秦氏が列島で豪族としての地位を固めると、彼らをたよって次々とテュルク系渡来人がやって来るようになり、九州の大分県には「秦王国」があったとされるほどである。彼らが倭国への侵入者と闘う場合、西突厥に援軍を求めるのは、けっして不自然な話ではない。
『書紀』は、突厥との外交の事実を極力伏せているため、達頭からの返書を持ってやって来た西突厥の使者も「高句麗の使い」とされている。
『書紀』の記述を要約する。
571年に高句麗の使いが越の海岸に漂着。
欽明天皇の病状悪化のため、彼らは山城(京都)の館に待機させられ、翌年、敏達が即位してから彼らの国書や調物が検分された。
彼らの文書はカラスの羽に黒で書かれていて誰も読めなかったが、百済の王辰爾(おうじんに)という者がこれを炊飯の湯気で蒸し、絹布に写して解読した。
「欽明天皇の病状悪化」とあるが、欽明=聖王はすでに554年に戦死し、蘇我稲目も571年に死去していた。
敏達が即位するまでカラスの羽に書かれた機密文書が検分されなかったのは、当時の倭国が大王不在だったことと、この文書が、西突厥可汗・達頭から威徳王=敏達への返書だったことを暗示している。その内容は『書紀』には書かれていないが、援軍要請に応じるという返事だったのだろう。
また、このときの使いは倭王への調物を地方豪族に盗られそうになったり、帰国の際に副使らが大使を殺すといったゴタゴタがあり、572年にも、新たな「高句麗の使い」2名が、朝廷側の人間に海に投げ入れられるという事件があった。こうした妨害は、倭国内に西突厥軍の介入を危惧する反対派勢力が存在したことを意味している。
しかし、西突厥の使者を殺したことで、かえって西突厥に、倭国へ軍事介入する口実を与える結果になってしまう。
カラスの羽に書かれた文字を解読した王辰爾は、もともと貿易氏族だった蘇我氏に雇われていた渡来人である。蘇我氏が実権を握ったことで、貿易業務のみならず、外交面でも重用されるようになったわけだが、この人も突厥人だったのかもしれない。
620年に聖徳太子によって編纂された『国記』と『天皇記』が、645年、蘇我蝦夷によって両方とも焼かれそうになったとき、船史恵尺(えさか)が『国記』を奪い取り、中大兄(天智)にたてまつったという。王辰爾は、この船史(ふねのおびと)の先祖である。
秦氏が応神と継体・欽明、そしてのちの聖徳太子を結び、王辰爾の一族が聖徳太子と天智の間を結んでいるという構図に注目していただきたい。
また、蝦夷が『国記』を焼こうとしたという話は、それが『書紀』の原案であり、『書紀』が蘇我王朝の存在を抹消していることを暗示する演出だったというのは、私の考えすぎだろうか。
真興王の死
572年、威徳王は新羅軍を倭国で迎撃するために来倭。『書紀』はこの年を敏達即位としている。
575年、北九州に攻め入った新羅軍は思わぬ大敗を喫し、『書紀』にはこの年、「新羅が使いを遣わし調をたてまつった。恒例よりも多かった。同時に、もと任那であった四ヵ村の調をたてまつった」とある。明らかに新羅の賠償に関する記事である。
翌年、敗戦の責任を取らされたのか、真興王はこの世を去る。